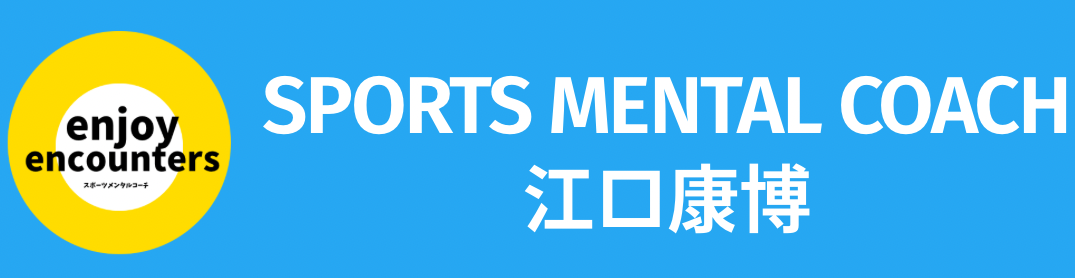こんにちは。スポーツメンタルコーチの江口康博です。
9月に入って少し涼しくなってきていますが、まだまだ暑さが続いていますね(本稿を書いたときは2025年9月)
連続猛暑日を記録するなど暑い日が続くなかのトレーニングで疲労が溜まっているアスリートも多いと思います。
アスリートのなかには「休む」ことに抵抗感を持っている方も多いと思いますが、そんな方は一度でも「休む」効果を真剣に考えたことがありますか?
もし「休む」ことに向き合ってこなかった方は是非このコラムを読んでいただきたいのです。
自分自身の固定観念が変わり、「休む」ことへの意識が持てると思っています。
今回はなかなか真剣に考えることが少ない「休む」ことについてです。
休めないのは日本人の文化?
日本ではオーバートレーニング症候群になるアスリートがいますが、スポーツの世界に限らず、日本社会の考え方、働き方の影響が少なくないと考えています。
●日本人の有給休暇取得率
米旅行予約サイト大手のエクスペディアが発表した世界11カ国・地域の有給休暇に関する調査では、2023年の日本の有休取得率は63%で世界最下位でした。日本の次に取得率が低いニュージーランドでも86%で日本の低さが目立ちます。
また、休み不足について日本の47%が「感じていない」と答えた。一番低いドイツ(16%)の約3倍で、世界で最も高くなっています。
世界の他の国と比較しても休まないお国柄なんですね。
仕事を休まないことで疲労が蓄積し、生産性・パフォーマンスの低下、メンタルヘルスの悪化、健康リスクの高まりもあると言われています。(他の要因も複雑に絡み合っていると思いますが)
●休むことに関する根強い考え方
このように休まない日本人ですが、社会でも、スポーツでも「休む」=「甘え」といった考え方が少なからず根付いています。
「休んだら周りの人に置いていかれる」「他のメンバーが休んでないのに自分が休むなんて」など一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
また、部活や長時間労働の文化もまだまだ存在し、スポーツいうと平日は長時間の練習、土日も試合や遠征でオフの日がない、なんていうケースも多いです。
指導者やマネジメントの立場の人間も「休息の重要性」を理解している人が少なく、休息は軽視されがちです。
併せて、「根性」や「我慢」が美徳とされて、評価の対象となりやすいため、選手が自分で判断して休むことが簡単ではありません。
もちろん、上記のような環境ではないとしても、
みなさんの意識の奥底にも「休むのは悪」といった思い込みがありませんか?
特に責任感の強い人ほど「成長しなくてはならない」「チームのために頑張らないといけない」などと休息を取らずに自分を追い込んでしまうことが多いです。
休まずトレーニングを続けていると、疲労が回復しないまま蓄積し、筋肉や関節に負担がかかってしまい、「オーバートレーニング症候群」を代表に、パフォーマンスの低下、怪我のリスク、そしてメンタル不調にもにつながると言われています。
せっかくトレーニングを頑張ったのに「オーバートレーニング症候群で競技ができなくなり、回復に半年」などになれば、それこそ本末転倒です。
「休まないリスク」について頭ではわかっていても、チームメンバーや相手選手を意識したり、休む自分が許せなかったり、休めない環境があったりと簡単ではない方もいると思います。
まずは頭のなかに「休む」ことへの思い込みがあるということを理解してください。
「休む」ことの大き過ぎるメリット
「休む」ことのメリットについては世の中にたくさんの研究や事例があり、コーチが休む指導をしている環境もありますので、ここでは詳しく書きませんが、みなさんも理解しているのではないかと思っています。
まず、休むことについてスポーツ科学的には人それぞれ、個人差があると言われています。
例えば、個人の能力や目指す目標、費やすべき時間によって異ってきますし、休む時間は、トレーニングの強度と頻度によっても異なってきます。
ただし、科学的には、トレーニングで損傷した筋肉の修復、神経系の回復、そしてメンタルヘルスの向上に不可欠であり、「超回復」を促して身体のパフォーマンスを高めるとされており、1日か2日間、体を休ませることで、回復力が高まり、身体の進歩ができます。
トレーニングによりもたらされるメリットがありますが、トレーニングによる疲れを癒し、身体を適応させるためには、休養と回復が必要なのです。
そうです。「休みは必要」なのです。
とりあえず休むためにできること
では休むためにどうすればよいのか?
なかなか休めないアスリートも多いと思いますので、まずはいくつか実践できそうな方法がありますのでご紹介します。
1.短い時間で集中して練習に取り組む
短い時間でも集中した状態、適切な強度で質の高い練習をすることで、最大限の効果を得ることができると言われています。
欧州プロサッカーでは、練習は週3~4日で1回90~120分程度で、少ない時間だからこそ、徹底して効率よく練習をします。
その結果、実力やパフォーマンスが高いことは言うまでもありません。
また、集中した短い練習により、リラックスや休息の時間を取ることができ、練習の物足りなさが競技へのモチベーションを生む出します。
日本でも「長時間ありき」ではなく、練習を工夫しながら試してみて、練習時間を短くすることができるのではないでしょうか。
余談ですが、仕事でも夜遅くまで残業して頑張ったときよりも、よく寝た朝に作業に取り組んだときの方がパフォーマンスが高く、短時間で完成度も高かったことがあります。仕事もスポーツも同じことが言えますね。
2.自分に合わせたトレーニングをすること
「チームメンバーが頑張っているから」「対戦相手が練習しているから」と、オーバートレーニングをやってしまうアスリートがいます。
自分と他人では骨格や筋肉、身体がすべて違ってくるのに、他人のトレーニングと比較することに意味がありますか?
例えば、植物を育てる時にゴーヤとサボテンは同じ育て方をしませんよね。土壌、水やりの回数、日当たりなど全然違います。
あくまで自分の成長に目を向けて、自分に合ったトレーニングを意識しましょう。
そして「休息」も自分に合うように取り入れていけばいいのです。
大谷翔平選手(野球)は投手と打者を両立していますが、その裏には細かい体調チェックとトレーニング調整をしています。疲労が溜まっている時は強度を落としたり、リカバリーすることを優先したり、大谷選手ほどのアスリートでも無茶せず、体調や状況によって変えているのですね。
3.戦略的にスケジュールに「休息」を入れる
「休む」ことに抵抗感のある方は、「休息日(休む時間)」もトレーニングの計画やスケジュールに入れてしまいましょう。
負荷をかけるトレーニングの時間と、身体の回復させる時間を考えて、練習全体で最大限の効果を出せるように戦略的に「休息」を取り入れていくのです。
そう、「休むこともトレーニング」なんです。
この考えを持てれば、むしろ積極的に、より工夫して「休息」が取れると思います。
仕事や学習で「ポモドーロ法」というものがあります。
「25分の集中作業+5分の休憩」を1セットとして繰り返すテクニックで、集中力を高めて生産性を向上させる効果があります。
勉強やビジネスでも同じような方法があるのですね。
4.休憩を競技について考える時間にする
「休息」を入れている時間も、ただ休んでいるだけではなく、競技のためにできることがたくさんあることを知っていますか?
例えば、
あらためて自身の目標について、目標に達成するための計画、やってきた行動について振り返る時間がつくれます。
目標や行動計画の軌道修正したり、さらに改善できることなどがあるはずです。
ガムシャラに進んできたからこそ、ときには立ち止まって考える時間を設けることは成長には必要です。
競技に関する本や動画を見て研究や学習して知見を深めることもできますね。
自身の試合の動画、有名選手のYouTubeなどでも学べることはたくさんあります。
現在、取り入れようとしている動きや試している技があればイメトレなどもできます。
(ただし、うずうずしてトレーニングしないようにしてください笑)
※イメトレについては、イメトレに関するコラムも掲載していますのでご参照ください。
このように実際に身体を動かさないトレーニング、たくさんありますね!
まとめ
ここまでの「休む」ことについてポイントのおさらいです。
・日本人は休むことへ抵抗感を持っている
・休まないことで起こる恐ろしいマイナスの影響
・休むことにはむしろ成長に必要で、大きなメリットがある
・休むためにできる簡単な方法があること
このようにあらためて整理すると「休む」ことがとても重要で取り入れられることがわかったのではないでしょうか。
それでも、「こんなことは頭ではわかっているけどどうしても休めないんだよ」という方がいれば、下記の質問を考えて答えてみてください。
・その考えは本当に正しいのでしょうか?
・あなたの目標や目指す姿はなんですか?トレーニングすることが目標なのでしょうか?
・「休まずトレーニングすること」が本当に自分が目指す姿に向けた最適な選択になっていますか?
このように強く申し上げるのは、過度なトレーニングによる怪我やコンディション不良などで、成果が出せかった、競技ができなくなり苦しんだ方をたくさん知っているからです。
「そんなアスリートは絶対に見たくない」と思っています。
みなさんに一番伝えたいことは、
「休む」ことで「もっとこの競技をやりたい!」と競技の楽しさをあらためて思い出してもらいたい
ということです。
それはアスリートの競技人生だけではなく、その方の人生全体にもプラスになると考えています
私たちスポーツメンタルコーチはこんな想いでアスリートのサポートができるように活動しています。
最後までお読みいただきありがとうございました。