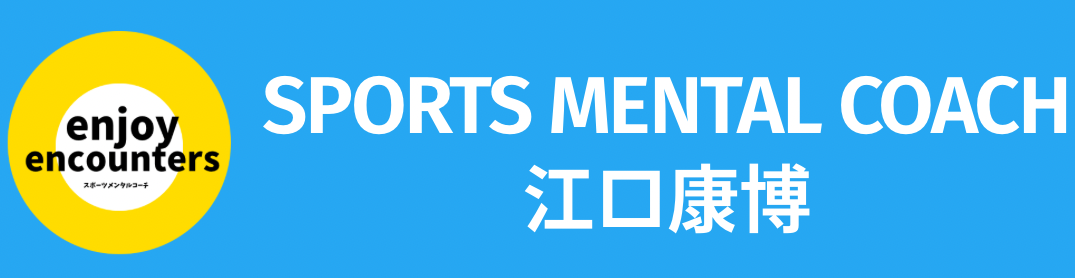こんにちは。スポーツメンタルコーチの江口康博です。
競技をするなかでこんなことを思ったことはありませんか?
「今週はあのトレーニングができなかったから負ける」
「今日は試合前のルーティンにキレがなかったからダメだ」
「あの人のように走り込まないと強くなれない」
アスリートや競技をしている方と話しているとこんな言葉をよく聞きます。
果たしてこのようなに思っていることは本当に正しいのでしょうか?
(思っている方はちょっとだけ時間を取って自問自答してみてください)
実はこの「やらないといけない」ということは本人が思い込んでいるだけで事実ではありません。
正確には「100%事実とは言えない」ということです。
もちろん、それで結果につながることもありますが、この思い込んでしまうことで、試合での不安になる、大会前に常に悩んでしまう、無理にトレーニングして怪我につながるなどマイナスに働いてしまうことが多くあります。
とても良い機会だと思うので、今回はご自身でも考えながら読んでいきましょう!
成功体験が誤った認識をつくる
よくあるのが、成功体験があったからこそ、間違った認識が植え付けられてしまうことです。
過去に成功した体験から「次もそれをやれば勝てる」と思い込んでしまうことです。
特に経験の浅い若年層のアスリートは「一度成功したら、このやり方で次も成功する」と思い込んでしまう罠に陥りがちです。
1.勝利した(成功した)原因はわからない
勝利したこと、うまくいったこと、成功したこと、の要因を特定することは簡単ではありません。
そのときの体調やメンタル、チームメンバーの調子、相手のコンディションなど多くの要素が重なってうまくいった可能性があります。
また、10回やって1回の成功がたまたま今回に来ただけかもしれません。
うまくいった要因があるにしても、同じ試合で間違えたこともやっていたかもしれませんね。
ただし、みなさん勝利の際はあまり分析をしません。
スポーツの世界では結果が全てという考え方があまりにも強烈で、結果が出ていれば全て肯定されてしまう傾向にあります。
ただ、多くの方は、経験のなかで一度そのやり方で成功する(成功体験を見ると)と、振り返りや内容の分析を行わずに、「これをやれば勝てる」と思い込んでしまい、毎回それをやるようになります。
私たちスポーツメンタルコーチでは、これを「成功体験の誤学習」と呼んでいます。
例えば、特に多いケースが、たくさん努力したから結果が出たことで「努力すれば結果が出る」と思い込んでしまうことです。
努力しても結果に結びつかないこともあります。特に年齢を重ねると努力の質も関係してきます。
2.同じ練習、同じ考え方になってしまう
成功体験に囚われると、「この練習をやらないといけない」と自身の頭のなかに強烈に刷り込まれてしまいます。
そうすると、自分で考えることや工夫することを放棄してしまい、この一つの考えだけに支配されてしまいます。
自身のフィジカルや体調、年齢も変化していくなかで、本来であればトレーニング方法など変えていくことが多いのですが、この思い込みは非常に危険です。
そして、新しいことにチャレンジしようという考えもなくなり、本来変わることで成長できたかもしれないのに同じことを続けて伸び悩んだり怪我をしてしまいます。
強い思い込みは、考えることを放棄させ、人の成長の機会を奪ってしまいます。
3.「これをやらないといけない」と思い込みがメンタルに悪影響を
成功体験の誤学習では「この練習をやらないといけない」という義務感がメンタルにマイナスに働いてしまいます。
試合に向けた準備や日々のトレーニングでも、「やらないといけない」と思い込み、もしできなかった場合は自分を責めてしまいます。
例え、それが自分に合っていない内容、傍から見ると毎日続けるにはハードな無茶なことなどでもそう思ってしまい、いたずらに自分を落ち込ませることになります。
また、試合前にできなかったときは「あの練習ができなかったからこの試合はダメだ」と思ってしまい、試合中に気になる、不安になるなど、本来のパフォーマンスを発揮できない場合もあります。
ただm少しご自身の経験でも思い返してみてください
「調子が悪い時でもなぜか勝てた」「怪我で思うようにトレーニングができなかったけど大会ではいい記録が出た」ということってありませんか?
プロアスリートは調子の好不調を整えて準備をするので、あまり調子に言及することは少ないですが、怪我や体調不良でパフォーマンスが落ちるだろうな、と思っていても、結果を出す選手は多いですよね。
WBC2023で大谷翔平選手は開幕前に右足首の違和感や準備不足がありましたが、大会では圧巻の投打で日本を優勝に導き、最後はトラウト選手を三振で仕留めて伝説をつくりました。
トレイルランニングの世界でも、「大会前に怪我で走り込みができなかったが、本番では良い走りができた」、「レース開始直後に胃腸トラブルでリタイアも考えたけど、結局復活して優勝した」などと言うトップ選手も多くいます。
準備に力を入れることは重要ですが、決まったことに固執しなくても実力を発揮できることがあります。
このように、どんな状況でも「なんとかなる」というメンタルが重要です。
「結果を出している人がやっていること=自分もやれば結果がでる」ことはない
活躍するプロアスリートや周囲で結果を出している選手を見ると、そのやり方を模倣してしまうこともあります。
この考え方を持っているアスリートは本当に多いです。
自分とはフィジカル、メンタル、経験など自分とは違う要素が多すぎるのに、考えずにそのまま真似てしまうことは危険です。
そのアスリートも他の複数のトレーニングやストレッチなど併せてやっているかもしれません。専属トレーナーから正しい指導やケアを受けながらやっている場合もありますので、一つのやり方にとらわれずに総合的に検討していく必要があります。
Aさんが上手くいったことは、Bさんも上手くいくとは限らない、ということです。
一つの方法として検討すること、参考にすることは重要ですが、「これができなければならない」と思い込まずに、自分の身体や特徴に合わせて取り入れていきましょう。
準備にあたってどのようなメンタルが必要か?
では、日々の練習や準備にあたってどんなメンタルを持っていけばよいのでしょうか。
1.客観的に見る力を養う
自分自身を俯瞰的に客観的に見る力が重要です。
そのためにはまず自分を知るということ。自分の現在地や状況を客観的に捉えます。
目指す姿になるために、伸ばしたい、足りない部分など、今の自分に必要なことを知ることです。
そのためには、周りの人や情報に振り回されないように、自身の心もしっかりとコントロールできないといけません。
2.新しいことを検討してみて良ければ試してみる
自身をコントロールできたら、一つのことに捉われず、色々な方法を試してみることです。
人の身体は本当に何が良いのか個人によっても差があります。競技のレベルやステージ、年齢によっても変わってきますので絶対的な正解はありません。
試してみて、良ければ取り入れる、悪ければやめる、ぐらいの考え方でいいのではないでしょうか。
このPDCAを回していくことで活躍するプロアスリートも多くいます。
ノバク・ジョコビッチ選手(テニス)は、食事・睡眠・メンタルを含めた自己管理を数値化し、常に改善しています。試合後の分析で戦術の修正を入れ、次の試合で試す。この繰り返しで常に「進化する選手」としてベテランでも第一線で活躍しています。
3.自分を信じること
自分がこれまでやってきたこと、これからやっていくことに自信を持つことです。
うまくいかないとき、結果が出ないときは、どうしても自分のやっていることに自信が持てずに、心が揺らいでしまったり、何かに執着することで、現実から、考えることから逃がれようとしてしまいます。
そんなときは自分がやっていること正しいと思いつつ、「間違っているのかな?」と疑いながら、考えていくことが重要です。
自分でも毎日振り返ることや、コーチなど周囲に頼りながら、今の自分にできること、できるだけの努力を行動していれば、後悔がなくプレーできるようになります。
イチロー選手(元プロ野球選手)の言葉です。
「結果が出ないとき、どういう自分でいられるか。決してあきらめない姿勢が、何かを生み出すきっかけをつくる。」
また、自分を信じるためにも目標設定をしっかりと行い、目指す姿をイメージすることがブレない自分をつくるためにとても重要で、結果に相応しいメンタルを持つことが結果を生んできます。
※目標設定についてはコラムを参照ください。
コラム「結果を出すために最も重要で、そして楽しい「目標設定」について」
まとめ
「~しなければならない」という思い込みについていかがでしょうか。
我々人間の身体は、脳を含めてたくさんの謎があります。
人体は機械やプログラムではないので、指示を与えればいつも同じ動作ができるわけではありません
コンディション、外気の温度、疲労、食事、その他の環境の影響があり、今日と明日でも全く同じ自分が存在はしません。
その中で一つのトレーニングに執着するとどうなるでしょうか。
目標に向けて決めた毎日のルーティンは別として、私は毎日の体調に合わせてトレーニングを考えて実行しても良いと考えています。
数々の国際的な大会で優勝し、世界最強のトレイルランナーと言われているコートニー・ドウォルター選手の言葉です。
(トレランを知らない方が多いと思いますが、トップアスリートのなかでも面白いと思った言葉ですので紹介させていただきます)
「私はコーチもいないし、トレーニングプランもありません。でも、自分の身体が週にどれだけのトレーニングをこなせるか、どのタイプのランニングが好きか、この数年間でわかってきました。毎日、自分の脳と脚の感覚をチェックして、そこから走る距離や強度を決めています。」
自分の心や身体の声にどれだけ耳を傾けることができるか。
疲れを、悲鳴を、成長を、ワクワクを聞いてみる。
その上で、現在の自分に最適なものをチョイスしていくことができればいかがでしょうか。
最後に、自分でわからないことは、専門家に頼ることも方法です。
フィジカルの問題であれば監督やコーチ、栄養に課題があればスポーツ管理栄養士に話を聞く、メンタルであればスポーツメンタルコーチがいますので、それらを頼って自分の成長にとってプラスにできたらいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。