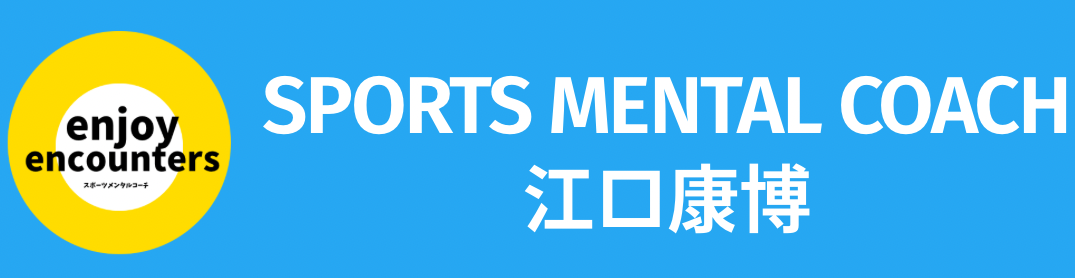こんにちは。スポーツメンタルコーチの江口康博です。
アスリートから、「自信がない」という声をよく聞きますが、そもそも「自信」とは一体なんなのでしょうか。
私も仕事などで「自信」があるときと、ないときがあります。
あるときはためらいもなく物事に取り組めて、進めている間も迷いなく仕事ができ、完了できます。
逆に自信がないときは、行動に移すのに時間がかかってしまったり、判断するときに迷って止まってしまうことがあります。
みなさんにもこんな経験ありませんか?
今回はこの「自信」に関する理解を深めていただき、自信を高める方法を知っていただきたいと思います。
■「自己効力感」と「自己肯定感」
「自信」とは、心理学的には心理学者のアルバート・バンデューラが提唱する「自己効力感」が一番近いものになり、メンタルの世界では正しい用語とされています。
もう一つ、似たような言葉で世間では「自己肯定感」という言葉が良く言われていますが、こちらは心理学の用語にはなく、造語になります。
①自己効力感とは?
ざっくり言いますと、自分の内側から自然に湧き上がってくる自分を信じる気持ちで、「なんかできそう」「うまくいきそう」という感覚です。これが「自信」と言われているものになります。
「自己効力感」(自信)は、人が新しく何かに挑戦するときに、行動するか否かを決定するための重要な要因の一つです。
「自己効力感」は、人が行動や成果を求められるときに、自分自身に遂行する能力、成果を出す能力があると認識できるかどうかを判断する基準になります。
すなわち「自分は達成できる」「自分には能力がある」という確信があれば、「自己効力感」が”高い”状態にあり、行動に移すことができます。
逆に「自分には無理だ」「自分には能力がない」と考えていれば「自己効力感」が”低い”状態となり、行動に移せない状態にあります。
②自己肯定感
一方、こちらは自分を肯定する、自尊感情、ポジティブ感といったものです。
「自己肯定感」を高くすることは自己を尊重し、自身の価値を感じることができ、自身の存在を肯定することで、「自分ならできる」「絶対にうまくいく」といった思いを強めていく行為です。
私は、この自己肯定感を高める行為はあまりおススメしません。
本来の自分(現在地)に目を向けず、自身を高めていくことから目を背け、いまの自分の上に理想の自分を塗り固めていくようにしてしまうからです。
そうすると、あるとき心がポキっと折れやすくなる方が多くいます。
■自己効力感の高い人
自己効力感が高い人にはこんな特徴があります。
・新しいことに積極的に挑戦する
・実行に移すまでが早い
・ミスをしても過度に落ち込まない
・できない理由より、どうすればできるかを考える
・前向きな発言が多い
・周りから学ぶ姿勢を常に持っている
自分が「なんかできそう」と思うことで、目標に向かうためにシンプルな考えや行動ができるようになります。
物事に取り組んでいく際にとても大きなメリットになります。
周囲の方で「あの人は自信持って競技に打ち込んでいるな」と思う人を思い浮かべると、上記の特徴があてはまるのではないでしょうか。
プロアスリートの考え方や行動を聞いていても、当てはまることが多いと思います。
■自己効力感を高める5つの方法
では、自己効力感を高めるためにはどうすれば良いのでしょうか。
主に下記の5つの方法があります。
①達成経験
自分自身で目標を達成した経験をすることです。
過去に達成した経験を持つことで、「次もできる」と思えます。
こう言うと、大会優勝、新記録など、すごく大きな達成経験がいるのかな、と思う方もいると思いますが、小さな成功体験でも全然構いません。
これまで自分が少しでもできたこと、成長できたことを細かに書き出してみましょう!
(練習で取り組めたこと、試合でできたこと、先月までできなかったことができた、など)
思い返してみると、小さな達成経験が多く、「意外と色々あるじゃないか」となると思います。
②代理経験
他人ができたこと、やっていることを、見る、聞く、動画で見るなど観察した経験です。
人は誰かができると、自分もできると思うようになります。
実際に過去にもこんな例があります。
・フィギュアスケートで難易度が高い技に成功した選手が出ると他の選手も続々と成功する。
・陸上で長らく記録が破られなかったが、1人が新記録を出すと、同じ年に複数の選手から新記録が誕生する。
・サッカーで海外で活躍する選手が出たあとに海外移籍する選手が増える、など。
なかなかできないことでも、他人が達成すると、「できない」という思い込みのフタが外れて、「自分でもできる」と思うようになり行動していきます。
手軽にできることですと、テレビやYouTubeなどの動画でプロの選手のプレーを見たりするのもいいですね。
③言語的説得
自分にそのスキル、能力があることを言語的に説明や説得されることです。
信頼する監督やコーチに「あなたの能力なら●●●ができる」と言われると、「そうか、できるのか!」と自信が付いたことがあると思います。それです。
④生物的情緒的高揚
体調やパフォーマンスの状態などモチベーションをアップさせることです。
試合前のルーティンやアップの準備運動などです。
⑤想像的体験
「イメトレ」です。
自分がプレーすること、達成することを具体的にイメージする体験です。
イメージをすることにより脳が「自分もできる」と思うようになり、行動に移していけます。
※イメトレについて詳細はコラムをお読みください。
<コラム>
同じ練習でも成長に差が付く「イメトレ」とは?
別のコラムでご紹介しましたが、私自身もこの5つのポイントがあったからこそ、完走率30%の100mileレースを初挑戦で完走できたのだと思います。
<コラム>
100mile(160km)レースを初挑戦で完走できたメンタルとは?!
■まとめ
「自信」について、いかがでしょうか。
実践するといきなり自信がつく、というものではありませんが、少しずつでも自己効力感を高めていくと物事への捉え方が変わってきます。
そうすると競技への取り組み方が変わり、結果が付いてくると思います。
なによりあらためて”競技の楽しさ”を再認識できるのではないでしょうか。
嬉しいことですよね。
最後までお読みいただきありがとうございました。