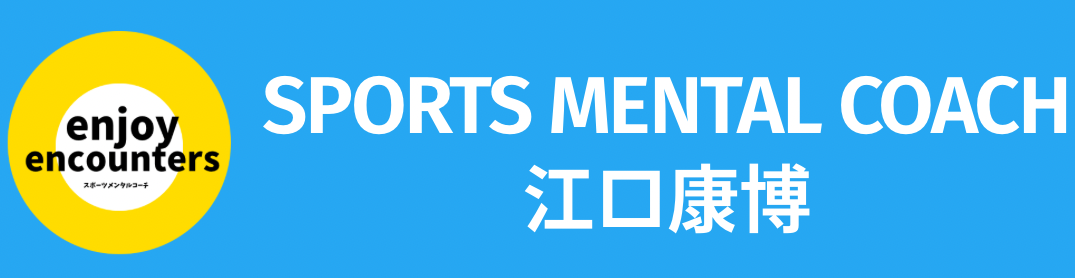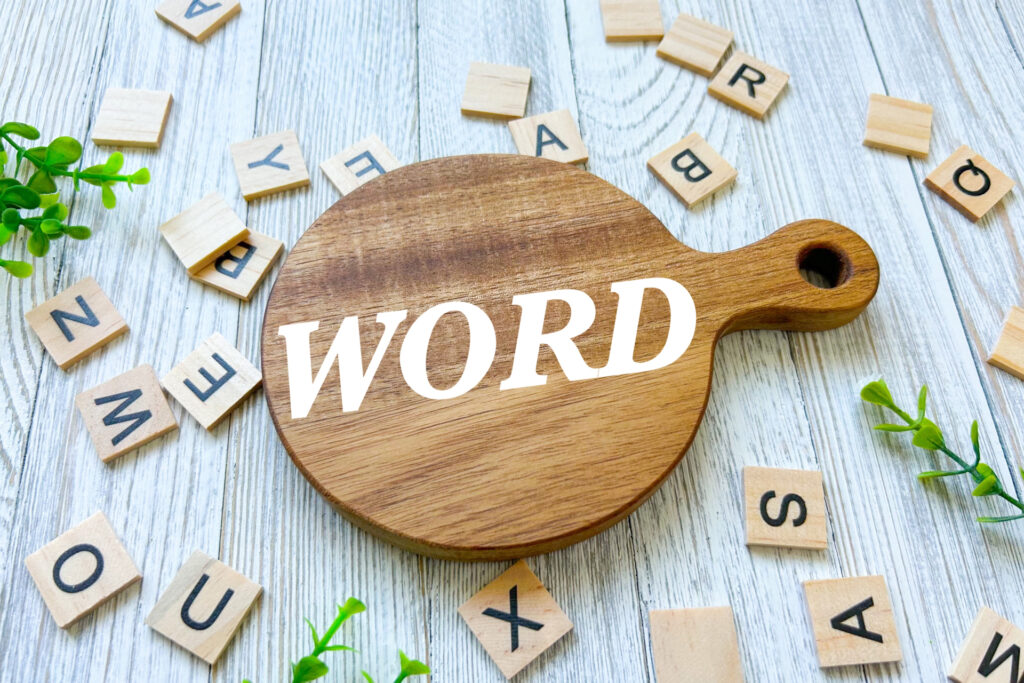
こんにちは。スポーツメンタルコーチの江口です。
選手には、よく「言語化」について悩んでいる、または課題に思っている方がいます。
近年、スポーツ界では、感覚だけではなく自らの言葉で説明できるように、他人に伝えられるように「言語化」することが求められる傾向にあります。
言葉にはとても強い力がありますし、言葉にしないとわからないこともあります。
ただ、私はすべてを言語化する必要はないと考えています。
言語化した方が良いもの、無理に言語化する必要がないもの、を分けて考えれば良いのです。
言語化化についてモヤモヤしている方は、ぜひ読んでください。
人間が言語化する目的とは
ちょっと根本的なところから見ていきましょう。
人間が言語化を行う理由は、コミュニケーションの円滑化、思考の整理、感情の理解と制御、そして自己理解の深化など、多岐にわたっています。
1.コミュニケーション
自分の考えや感情を明確に表現し、相手に正確に伝えるための手段です。
お互いの認識やズレを防ぎ、効果的なコミュニケーションが可能となります。
2.思考の整理
頭のなかでぼんやりと浮かんでいる考えを整理し、構造化するのに役に立ちます。
言葉にすることで思考の不明瞭な部分を明らかにして、より深く理解することができ、客観的に見つめるともできます。
3.感情の理解と制御
自分の感情を言葉で表現することで、感情の根本要因を特定し、感情の起伏をコントロールしやすくなります。
4.自己理解の深化
自分の思考や感情、価値観などを言葉にすることで自己認識を深め、自己成長を促すことができます。
これが一般的な言語化する目的です。
コミュニケーション面、自分自身の理解の面で効果があります。
他人と共有したいことは”伝えるために”言語化する
競技において「言語化」する目的はなんでしょうか。
自分の考えを他人伝えたいとき、共有したいときに言語化することが多いと思います。
例えば、チームの「戦術」や「戦略」などが言語化する対象にあたりますね。
チームメンバーが、同じ認識をしないでプレーしていると、みんながバラバラな意図を持ったプレーをしてしまい、チームワークどころではなくなりますね。
ですから、「戦術」や「戦略」などチームメンバーに伝えたいことは、チーム間の共通認識として、相手に伝わりやすいように言語化する必要がある代表的なものです。
アメフトの試合では、チームの中で明確に戦術として決められたプレーから、選択して進めていきます。
また、サッカーでも決まり事や戦術に関することはコーチや監督、選手自身も言語化していく傾向にありますね。
新しい言葉も出てきます。
サッカー日本代表チームでは、得点チャンスにつながりやすいピッチ中央でのパスを「花道」と呼んで、選手間の共通認識にしていますね。
このように、相手に伝えたいこと、共通認識は、意図的に言語化していく必要があります。
もちろん、どこまで明確に言語化するかは、競技によって、またチームの方針により変わってきます。
無理に全部を言語化しようとせずに、「どこまで言語化するか?」を考えることもとても大切だと思います。
自身の技術やプレーは言語化して伝えないといけないのか?
よく自身のプレーや技術も言語化する風潮にありますが、
私はすべてを言語化する必要はないと考えています。
監督やコーチであれば別ですが、選手が自分の持つ技術やスキルをすべて言語化して、他人に伝える必要があるのでしょうか。
そもそも、選手が持つ技術は、その人の身体、経験、頭脳を前提として、その人が持つ特有の条件のもと成立しているもので、それを他人に100%正確に伝えることはほぼ不可能でしょう。
また、デメリットもが多くあると思っています。
・多人数がわかりやすくなるように言語化すると、伝える側のオリジナルな意図ではなくなってしまい、最大公約数的に陳腐な表現になってしまいかねません。
・受け取る側も全く同じイメージで受け取ることはできません。
技術や感覚については選手毎に異なるからです。
逆に、受け取った側が変に意識して取り組もうとすると、本来の良さが失われることも危惧されます。
・また、その陳腐化した言語化を重ねることで、伝える側の選手自身も本来のオリジナルな感覚や良さが失われてしまうことも危惧されます。
このようにすべてを言語化しようとすると、伝える側、受け取る側の両方に取ってデメリットが多いように思われます。
自身にとって言語化する方が良い場合は?
ただ、自分のプレイや技術に悩んでいる方、改善したいと思っている方は、
自分自身のための考えや技術の整理、改善のために言語化することは良いと思っています。
言語化するときは、無理に言葉をきれいにしようとしなくてOKです!
むしろ”感じているそのまま”を言葉に表現しましょう。
感覚的な技術や感触などを、そのまま感覚的に言語化することで、自分のなかで「こういう状態」という定義し、変えるときや改善するときなどの指標にしてはいかがでしょうか。
大事なことは自分自身がその言葉の持つ意味や意図を理解して「言語化」していれば良いのです。
例えば陸上の長距離選手ですと、
「地面を蹴るのではなく、自転車をこぐように脚を回していく」
というような表現がよくありますね。
これも人によって捉え方が違いますが自分自身が「この走り方」という理解ができていればいいのです。
プロ選手が言っている技術の説明でも、本人にしかわからないものも多くあります。
長嶋茂雄さん(野球選手・監督)は、独特な表現する方の代表例としてよく紹介されますね。
(実際はかなり緻密に考えられていたとのことですが)
「球がこうスッと来るだろ、そこをグゥーッと構えて腰をガッとする。あとはバァッといってガーンと打つんだ」
ロベルト・カルロス選手(サッカー)も得意なフリーキックの打ち方をこのように表現しています。
「足をボールにこするように当てて、小指、薬指、中指を引っ掛けてキックする」
なんだか、わかるような、わからないような表現ですが、本人の感覚の表現が多くを占めていますね。
それでいいのです!
技術について言語化する、そうすることで自分が自分に対して説明(理解)できれば充分だと思います。
これが無理に他人に伝えようときれいな言葉にすると、違うものになってしまうでしょう。
自分の気持ち、感情は言語化してみよう!
競技をしていて「この感情はなんだろう?」とモヤモヤすることはありませんか。
そんなときは自分の感情を言語化して整理してみましょう。
・いまどんな感情を持っているのか?
・なぜその感情になったのか?
・その感情を持つことで自分にどんな影響があるか?
言葉にして考えることでぼんやりと考えていたことが整理されて、心のモヤモヤが軽くなると思います。
特にネガティブな気持ちや感情が出てきたときに、名前を付けて擬人化して、距離を置いて客観的に見る方法もありますね。
「試合になると不安になる君(くん)」
「相手を怖がってしまうさん」
「他人と比較してしまう君(くん)」
など。
ネガティブな感情を擬人化すると、セルフコントロール能力が上がる、とも言われています。
客観的に自分を見つめ直すきっかけになるので、モヤモヤする方は試してみてはいかがでしょうか。
まとめ
「言語化」すること、言葉にすることはとても大きな力があります。
人は言葉にしないと概念が持てないと言われています。
例えば、
「エモい」という表現は1980年代頃からもともとあった表現ですが、2006年頃から広まり表現方法の一つとして定着しました。
定着しないときは多くの人が理解できない言葉でしたが、若年層を中心に広がり、現在はある程度社会に浸透しています。
「暑熱順化」という言葉も、従来は専門家やスポーツ関係者の間で使われていましたが、2020年頃から熱中症対策の重要性が高まるについて報道に使われ、一般人も使うようになりました。
その他、日本語にあって英語にない表現など、使う言語で表現できるものが違ってきますね。
言葉があると共通認識ができることは、人類にとって大きなメリットです。
しかしながら、繰り返しますが、すべてを言語化する必要はないと思っています。
それに、なんでもかんでも言葉にして片付けてしまうのではなく、感覚的なこと、感じること、ぼんやりと思うことなどがあって良いと思います。
選手間でもお互い言葉を交わさず「プレーで分かり合える」みたいなことありますよね。
スポーツの他にも、芸術(アート)や映画、音楽、食事、景色、人など、理由は言葉で説明できないけど「なんか好きなんだ!」と思うことも沢山あります。
最後に、
カチッと言葉や形になっていない”なんとなく”があった方が、世のなか楽しくないですか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
◆体験メンタルコーチング
「言語化」は、
競技の技術的な側面だけではなく、
自分のメンタルを深く理解して、
より良いものにするために、
とても重要なことです。
スポーツメンタルコーチングでは、
アスリートが自身がモヤモヤする部分や、
うまくいかないと思っていることを
一緒に言語化して、整理していきます。
競技へ取り組む気持ちや思いで悩んでいたら、
相談してみませんか?